相続登記のQ&A



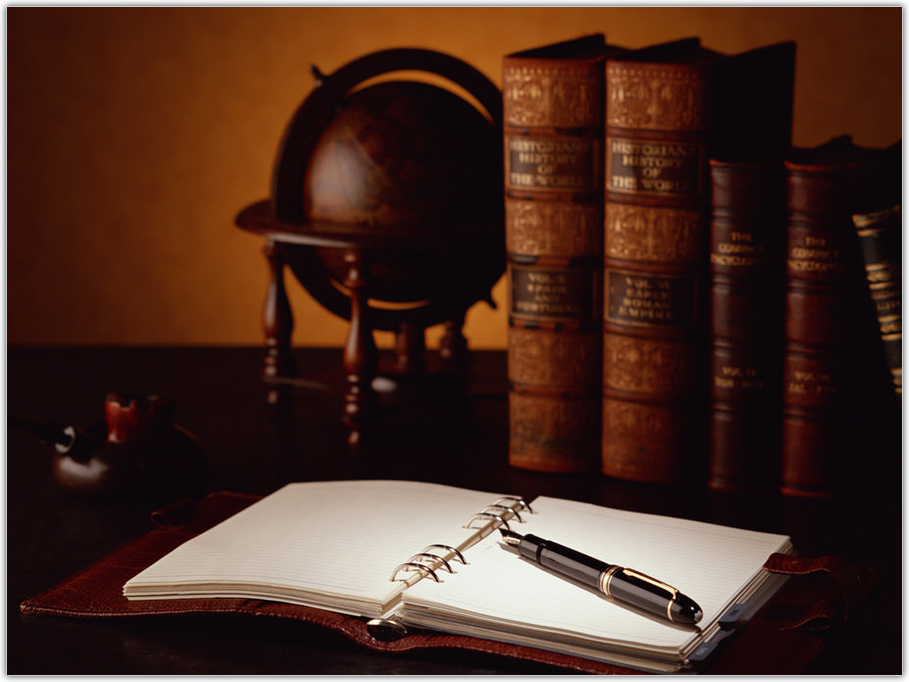
[遺言書]
Q 11.遺言書が残されていた場合は?
Q 4.司法書士に依頼せず、自分で相続登記をすることはできないの?
A 相続登記をご自分でやることは、時間と労力をかければできると思います。
まず、ご自分で必要書類一式を集めましょう。次に、登記申請書・相続関係説明図、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。最後に、念のため、法務局の相談窓口で確認してもらいましょう。実際、このような相談をされている方をたまに見かけます。相談窓口でOKがもらえれば、不動産登記申請の受付に提出して終わりです。
しかし、法務局で相談した結果、やはり手に負えず周辺の司法書士事務所に駆け込まれる方のお話もよくお伺いします。そうなると、せっかく時間と労力を掛けたにもかかわらず、司法書士報酬も支払うことになってしまいます。
ご自分で、できるか、できないかの判断はなかなか難しいと思いますが、そのようなご相談でも、お答えできる範囲で回答いたしますので、よろしければご相談ください。
Q 5.法定相続人や法定相続分とは、誰がどれだけ遺産を取得するの?
A 相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。
相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は以下の表のとおり、配偶者と一緒に相続人になります。
| 順位 | 相続人 | 代襲相続 |
| 第1順位 | 子供 | あり。子供が既に死亡していた場合、子供の直系卑属(死亡した人の孫、曾孫など)が相続します。 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) | できない。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | あり。兄弟姉妹が既に死亡していた場合、兄弟姉妹の子供(死亡した人の甥、姪)が相続します。 |
法定相続分
| 相続人 | 取得する持分 | |||
| 配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
| 配偶者と子供がいる場合 | 2分の1 | 2分の1 | × | × |
| 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 3分の2 | - | 3分の1 | × |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 4分の3 | - | - | 4分の1 |
表中の‐(ハイフン)は、相続人(代襲者含む)がいないことを表しています。 ×は、相続分がないことを表しています。
なお、子供・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、原則、それぞれ均等に分けます。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人の場合、子供の持分は各4分の1になります。
Q 6.遺産分割協議のやり方に決まりはあるの?
A 遺産分割は、お亡くなりになられた方(被相続人)が遺言で禁じた場合を除いて、共同相続人全員の合意によってすることができます。民法は、その要式について何らさだめていませんので、書面である必要はありませんが、不動産の登記や預貯金の名義変更をする際には、遺産分割協議書が必要なので、通常は、遺産分割協議書を作成して、当事者全員が実印で押印します。
協議は、共同相続人全員出席のもと、合議によるのを原則としますが、相続人の一人が遺産分割協議書案を作成して持ち回りによって承認をもらっても有効です。
協議の内容についても制約がなく、共同相続人全員の合意によって自由に定めることができます。したがって、法定相続分等にしたがって均等に分ける必要はありません。たとえば、相続人の中の1人が何もプラスの財産をもらわないことにすることも可能です。
Q 8.未成年者が相続人にいる場合は?
A 未成年者が相続人にいる場合でも、法定相続による場合や、未成年者が遺言により不動産を取得する場合には、親権者に登記(名義変更)の委任状にご署名・ご捺印をいただけばよいので問題ありません。
しかし、遺産分割協議をする場合に注意が必要です。たとえば、父が亡くなったとして、母と未成年の子で遺産分割協議をする場合、子供のために特別代理人を選任する必要があります。(家庭裁判所に申し立てます。)
たとえ、自宅の名義を子供の単独所有にする(つまり母親が実質的に子供に持分をあげている)場合でも、親権者と未成年者が同時に遺産分割協議の当事者になる場合には、特別代理人を選任する必要があります。


